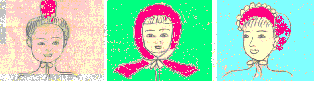
背景は、街道の風景
☆ ☆ドイツ人の日本人像☆☆ 幹線にあっても Steinau はローカル列車しか停まらない。 そして、この国の地方にはよくある風景だが、鉄道は町(村) 外れの小高い丘陵の中腹を走るから、駅から町へは丘を下って 田園を抜けながらたどり着く。 私たちは駅前で地図を開き、声を上げなら進む。タクシーな どいつも関係ない。 「これ、左が Bahnhof Strasse(バーンホーフシュトラーセ=駅道の意)や。 これをずーっと行けば交差点のはず。」と実地に地図を合わせ て確信を得ながら進むのだ。 坂は曲がりながら下った。下りきるとそこは平地で、まばら な人家や立木がなくなったところに信号の交差点があった。前 方と左右には牧草地が広がる。私の目にはそれが田圃のように 映る。 風景としては日本の田舎と変わらないし、交差点には丈夫で 大きいけれど、押しボタンが歩行者用にある。 過ぎて数百メートルで小川に橋がかかり、次第に家が多くな って町らしくなる。 辻の標識、「Bruder Grimm Str.(グリム兄弟通り)」に従っ て左折する。進みながら民宿めいた建物はないかと目で探す。 市庁舎前の広場を横切って Information があるはずの建物 に入ると、そこは礼拝堂のように静まっていた。奥に抜けると 一室に女性係員一人がいた。 彼女はよく分かる英語を話した。印刷物を数種類手渡し、そ の都度、町の各方面を指差しながら説明する。 「(ホテルは?)」 「(デンハルトに頼もうと思います。)」 「(そうですか。ここ、下の通りの薬屋の脇を下ればすぐです)」 「(有り難う)」 「(楽しんで下さい)」 と辞去するとき、印刷物のすべてを、 「STEINAU AN DER STRASSE」と鮮明にデザインされた白い紙の 手提げに入れてくれた。 観光の初めにまずホテルを確保するのが私たちの常で、広場 の下はBruderGrimmStr.、角の Apotheke(薬屋)の左脇の小径 に入ると、わけなくDenhaldに突き当たった。 「グーテンターク、ーーーグーテンターク!」と入り口に入ってから声を上げた が、返事がないので右奥に進むと、レストラン風にテーブルが 並びカウンターがあった。ちょうどおばさんがそこへ現れたと ころだった。 「ハーベンジー、アインツィンマー?」 「モメント、ビッテ」と言いながら奥の誰かを呼ぶと、主人とおぼし きおじさんが現れた。 「ドッペル、チンマー?」 「イエス」 「アイネ、ナッハト?」 「イェス」 「ゼーエンジー、ダスツィンマー?」と鍵を持って私たちを階上に誘う。 広くて清楚、トイレやシャワーも、窓の外の眺めも気に入っ た。 「ノインチッヒ」とおじさんは私たち二人を見入る。 「ミット、フリュースティック?」 「ヤー」 「九十マルク(6,750\)ならええやないか、朝飯付きで。はい、 オーケー。」 フロントまで戻ってチェックインをしたが、それは私が 「チェックイン?」と請求したからで、先方は鍵を渡せばそれでよし といった雰囲気だった。 鍵は二つ。一つは建物の入り口の、も一つは部屋のだった。 「ヴェンシュリーセンジイ、ダスハウス?」 「ナイン、ヴィアオフネン、ドゥルヒナッハト.」 部屋に物を置き、身軽に外出する。 「門限はないのやて」と、私はさっきの会話を妻に紹介する義 務を果たしながら最初の目的場所へときた。 高い壁塀に囲われた庭を有する建物、Heimatmuseum(Heimat =ふるさと)だった。元は裁判が行われた所で、グリム兄弟の 父が数年、判事を勤めるあいだ、兄弟は少年時代をこの地で過 ごした。 郷土資料やグリム童話に関する物を陳列する。法廷の形で保 存された部屋があった。私は、説明書きの分かる部分だけを拾 い読みをしていった。 当時の裁判を説明したものの中に、罪状の多くは、他人の畑 の作物を盗んだことだった、と書かれてある。私は罪人たちに どこか憎めないものを感じていた。 管理人は七十歳ぐらいの男女だったので、 「(グリムの血族)?」と、言葉や身振りを重ねて尋ねてみた。 「(いいえ、ただこの土地のものです)」 おじさんもおばさんも白人の青い目、白い髪で、私とは隔た った人種だが、<こういう人は私の周りによくある>実感があ った。 建物を抜けると、小川に木の橋が架けられていた。手前には 水車小屋が、今は明らかに使われてはいないが、残されていた。 川床は水車の水をコントロールすべく、石や三和土(タタキ)で堰 がしつらえてあった。 渡って小川の縁を歩く。ゆっくりと流れる水、岸の青草、と ころどころに洗い物のためか家鴨(アヒル)用にか、板の段が川面 にせり出している。川沿いの道は、両側に葉の多い樹木が並ぶ ので、木陰が路面をすっかり覆っている。 私はゆるやかに歩きながらシューベルトのリードの世界を思 った。「美しき水車小屋の娘」もこんなところの叙情なんだと 自分をイメージの中に置いて陶酔していた。 再び橋を渡り戻ると、細い道の右手には菜園が仕切られ、左 手には緩やかな流れが川床に藻を揺らせ、何かの芥を下手(し もて)に運んだりしている。 菜園で今働くおばさんに声を掛けた。 「(ジャガイモの草を取るの?)」 「(いや、虫、虫取り)」 ポリバケツに入れているから、よほどの虫なんだろう。私に はじゃがいもの虫取りなんて作業経験はない。 菜園を隣と区切る垣根は、木苺ふうの植物で、実が成ってい たりする。赤く熟したのもちらほらする。 「食べるられる?」と妻が問う。 「ええと思うんやが、ここは日本やないから、食べやんのがえ えに。」 無邪気な会話をしながら、再び人家の間に入り、城の方へと 坂を歩いていった。 町中は清潔に保たれている。見かける町びとたちは、並み以 上の関心を持ってくれているのか、通りを歩く私たちは家の内 から覗かれている雰囲気を感じ取る。 石畳の通りは午後の陽差しを返して眩しい。両脇にはトンガ リ帽子のような切り妻屋根に四層にも窓をしつらえて、窓それ ぞれに木箱プランターが花を咲きこぼす。木組みの家は白壁を 木柱で仕切るから、風景として目に快い。 白川郷の切り妻に通じてると感じながら、快い背景の前で 「ここで一枚撮ってえ」と私がモデルになり、「そこええ。そ の辺、立ってえ」と妻をモデルにする。 城のわき道の坂を登るとき、ザザーツと急ブレーキする音を 聞いた。近づいて道を折れると二百メートルばかりのまっすぐ な坂道だった。小学校一年生ぐらいの坊やが二人いて、小自転 車を交互に乗る。一人は流行のヘルメットを被る。そして彼は より大胆に、坂の上端からペダルを力任せに漕ぎ下って、下端 の手前四五メートルで急ブレーキ、と同時に右にハンドルを切 る。するとスキーの急停止のように、前輪がザザーツと横向き に土をこすりながら危うく、しかし勇ましく急停止する。 選手は交替して、坂上のスタート点に立ち「(見とれよー)」 とか何とか叫び声を上げ、力いっぱいの全速力体制に入るのだ った。全速力と急停止の練習、遊び、ゲーム。 男の子ならではの遊びだった。羨ましかった。忘れて久しい ものを、いまここに取り返していた。 私はかつて息子に自転車を買ったとき、五歳の息子と真剣に 向き合って「言った」のを思いだした。「絶対に道路で乗るな よ。」と。 道はまた曲がって壕の上の橋に出る。半ば渡って振り返ると、 城門が今や衛士こそいないものの「中世の風情」をして中の暗 い通路を見せている。渡り終えると、視野がさらに広がった。 それは中世劇の舞台装置のように円柱の煉瓦の建物に半円の黒 い瓦帽子を被せた姿の建造物が、メインのお城にいくつも付随 し取り巻いていた。 「味があるやないか。」 私はこの風景を持ち帰らない訳にはいかないと思った。 「復元したんやて。」ガイドブックの解説を妻は紹介した。 なるだけ全景を収めたいと少しずつ後ろに下がると、小学校 があった。運動場とは駐車場を隔て、そこからのアングルがい ちばんよさそうに思え、カメラでもビデオでも撮った。 子どもたちも羨ましい。放課になったら仲良しと三三、五五、 おしゃべりしながら堀の橋を渡って城門に入り、石畳を踏んで 城内の広場に出る。どこかの学校が遠足に来ていて、先生の説 明を聞いているそばを静かに通って、市庁舎前の広場で道草を 喰ったりしてから、家路を辿る。 マリオネットの劇場の所在はと、城内のインフォーメイションで尋ねよ うとしたが、もう閉まっていた。その時の私たちの会話を聞い ていたのか、坊や(クナーベ)がそばで何かを言った。 見ると先ほどの「暴走族練習予備軍(?)」だった。 「ヴォイスト、マリオネット、テアーター?」改めてボク(クナーベ)に聞いてみ た。 「***、**、**」言葉は理解できないが、元気よく指差しながら 方向を示す。言葉の中に「---ネッヒスト(とか)マインハウス---」とか 聞こえる。 「ついていくよ」とボクの後に従った。喫茶店の下の倉庫風の 建物にメニュー紙程度の掲示があった。 外題(げだい)が三十ほどもある。そしてそれぞれ料金が異 なるらしく、金額が書き添えてあるのだが、私の感覚には異常 に高いのだ。末尾に「日本語の説明いたします。通りの下の薬 屋まで」とあった。 私は倉庫風の建物を半周して、 「入り口、分からんなあ。ほんとにやっとるのやろか。」と言 いながら、もう一度、掲示物を見ると、最終の上演が 「16:00~」となっていた。多分、今日は観客がなく、開演し なかったのだろう。 薬屋へ行った。鍵がかかっていて、硝子戸をジャンジャンと ノックしたが、返事はなかった。 ホテルに戻って小休止したあと、まだよく見ていない坂の下 側の町で食事をしようとした。 先ほどのHeimatmuseumの壁塀の上に、四人の児童が上がって 大きな桜の枝から桜んぼをもいでいる。六七歳のあどけない児 童だった。塀は三メートルもある。どうやって上ったのだろう か。 妻はそばによって、「頂戴!」と手を差し上げた。 少年が黒く熟したのを選んで、手元にうまく届くように落と す。 少女は、恐れて腰が伸びないが、手の届いた枝からまだ赤み の浅いのをもいで、投げた。拾うと実の裏が青かった。 「なんて言うの?」 「ヴァスイストダス?」私たち二人は実を掲げて問う。 「キ 「キ**」**」と返事の合唱は乱れて聞き取れない。 「ゲープ、アッハト。ダンケシェーン」と子どもたちに別れて通りの方に向 かうとき、先ほどからこの様子を見ていたのか、一主婦がそば にきて、 「キルシェ。」と教えてくれた。 「ああ、キルシェ、キルシェ」と繰り返していると、 「アイネ、キルシェ。ツヴァイ、キルシェン。」と文法まで教えた。 「フィーレ、キルシェン」 佐藤錦に負けない艶と甘さだった。 通りへ向けてお肉などを置く惣菜屋さんがあって、片隅にテ ーブルを数卓だけ並べ、先客にはアベック一組がコーヒーを飲 み終えている。 入った。 「(夕食、たべられる?)」 「(はい)」と、店員兼ウエイトレスの愛想がいい。メニュー を読むと、当然ながら肉料理が多い。 暖かい料理が出された。 私のビーフステーキ、妻のポークステーキはそれぞれポテト が添えられて、グラスのビールで美味しくいただく。時々はお 互いの肉が卓上の皿越しに交差したりする。 ビールのおかわりを、もう二本要求して、陶然と賞味を続け るとき、教会の鐘が響きはじめた。 「夕べの鐘」とタイトルして絵にも詩にも、また歌にもなり そうであった。 鐘は数分間続く。私は知らず知らずその雰囲気に浸りきり、 グラスとナイフ、フォークを置いていた。 その時、ウエイトレスは素早かった。 (何の用?)といぶかる暇もなく、「ダンケ、シェーン」と、既にお 皿に手を掛けて言った。 「あ、待って。」私は半ば叫んだ。(理不尽な!)とばかり女 性の顔と皿とに視線を繰り返す。 「あっ!」ナイフとフォークが揃って右を向いている。(しま った) 「ノン、パザンコールフィニ、ーーーあ、いや、ノッホ、ニッヒト」頭は混乱しながら ももっと食べたいと主張するのは忘れない。 ウエイトレスは、笑顔を失わずに、皿を戻した。 ふと気づくと、他の店員が店を閉めはじめているのだ。(あ、 そうか)と感じるものがあって、ウエイトレスに「ジー、シュリーセン、 レストラン?」と問う。 やはりそうだった。 「イエス。キルヒェグロッケン*****」教会は今日の仕事の終わりを告げて いる。いや、一日の仕事の感謝の祈りなのだろう。 「(急いで食べるよ。)」と手と身振りで示すと、 「(ここは構いませんよ)ビス、アッハトウアー」と奥に下がった。 「八時までええ、ちゅうとる。そやけどうちらがおらなんだら 帰れるのやで、食事の終わりを今か今かって見とるのやに。」 皿の物を平らげ、ビールの泡滴の音を厭わず吸い込んで、 「ビッテエ!」と叫んだのは、それから五分も経ってはいなかった。 通りへ出ても、緯度の高い国での七時前は、日本の午後四時 にも思えない。私たちは歩いて再び小川に沿う並木の小径に来 た。 木橋を渡ると向こう岸の柳の下で釣りをする若者を見た。川 幅は四メートルほど、浮きをゆったり流す男に声を掛けたくな った。 「フィッシ?」 「ヤ」と肯く。 「ヴァスフュールアインフィッシュ?」 「ーー」 魚の名前なんか、外国語で言える訳がない。だがシューベル トの「鱒」は「Forelle」の訳で、ドイツ語原詩中には「Fisch- lein」とある。また諸訳の歌詞のうち「あゆ」とも唄われてい るから、この地に知られる名前だろうと「フォレッレ?」と声を上げ てみると、 「ヤアア」の返事が、やや苦笑いめいていたのは、釣果がさっぱ りであることを物語っている。 「ヴィーダーゼーエン」と手を振って別かれ、木陰を進む。 五十メートルほどの先にベンチがあった。一人の男が座って 本を読む。傍らに小型バイクがあった。 読書を邪魔をする気はない。「グーテンタク」と愛想を交わして 通り過ぎるつもりであった。 「What country are you from?」 「***--Japan」警戒心が返事を遅らせる。 「(英語を話しますよ、三歳児の英語だけど)」 「(私もです)」 「(気に入りましたか、ドイツ)」 「(ええ、特にこの町の自然に取り巻かれているのがいい)」 「(住むならここです。都会の汚さもないし、こう見えても必 要な施設はすべてある)」 「(そうですか。日本人はよく来ますか)」 「(よく見かけます。あなた達は団体ですか)」 「(いや、個人で、二人だけで来ました)」 「(何故ですか、日本人は個人ではなくて集団で考えますね)」 この時、猛烈な反発心が湧いている。 「(かつての日本はそういう傾向があったかも知れないが、今 は違う。私は私だ)」 ハーナウでは、園芸屋の看板に「SELBST ist SELBST」 と三段に書かれてあったのを見て、(なんだ、ドイツだって隣 りや世間が気になるのか)と思ったのを思い出し、 「(私自身がSELBST ist SELBSTと思って生きている)」と言 いきった。 「(いや、ここに来ている日本の企業主がこう言った。雇用さ れたら『会社と結婚する』のと同じだと)」 「(そんなの日本人としてもおかしい。私が会えば間違ってい ると彼に言いますよ)」 彼は、表情に笑みかニヤケかを浮かべ、自らの信じる日本人 像を変えたくないように見えた。とすれば個人で旅するやや変 わった日本人を相手に議論していることになる。 話題を変えた。 「(何をしているの?)」 彼は名刺を探して差し出した。 「サイコロジスト?」 「イエス」 しばらくの雑談を重ねて、写真も撮り、互いの手紙を約束し た。 「(私に手紙をくれると、白馬の騎士があなたの前に現れるか もしれない)」 「(え? 何の事?)」 「(冗談)」 いや単なる冗談ではない。皮肉や揶揄を篭めて言ったのだろ うが、私にはもはや強烈な対抗意識はない。この心理学者の過 剰気味な自意識を、この国の田舎風景の一部として観察(ウオッチ ング)していた。 「ヴィーダーゼーエン」 「レープヴォール」 小川を渡り戻って、菜園沿いの細道を歩くとき、バイクの激 しいエンジン音が始まり、暴走風に遠ざかるのを聞いた。 ☆ |
∮ Break Time ♪
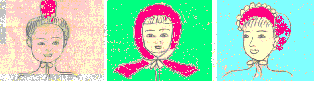
|
☆ ☆「赤頭巾ちゃん」の真実☆☆ Kassel駅で乗った列車は、前日と同じように二階建て車両だ った。もちろん階上に席を取る。小学生の遠足か社会見学だろ う、二十人ほどが同じ車両に座る。婦人の先生は、いつもみん なに注意を配っていた。だが口やかましくはない。児童は、し つけよく静かに座っている。ピアスや指輪など私にはなじめな いオシャレ飾りがついている女の子も、隣りあう者同士が喋る 程度で、車内がざわついたりは少しもしなかった。 人はしつけられ教え込まれて公序良俗を身につける。社会を 作るには、だから教育の人づくりが基礎になる。日本は、私の 見るところ「放し飼い」のままのヒトに手が加えられれていな い。「放し飼い」をそのままを放置すること、イコール「人権 尊重」だと浅はかにも信じる大人、そしてそれに意識的につけ こむ知能犯的な未成年もいる。 ドイツでみるこういう教育法を敢えて学ぶ必要はない。当然 のことを当然だとして人間完成の一要素に位置づけ、教師の当 然の仕事として児童に要求し続けさえすればいいのだ。 Fuldaで私たちは支線に乗り換えるべく列車を降りるのだが、 先生の合図で児童は数分早く席を立って、扉付近に向かう。そ の時、私たちのそばを通って階段を下ったが、彼らの幾人かが 私たちに挨拶してゆくのだった。 「ヴィーダーゼーエン」、「ゼーエン」と口にするから、私も挨拶を返 していた。 私は五十年以上も前の、つまり敗戦前の村の国民学校で、先 生からよく言われていたことを思い出していた。 (センセに出会ったら、なんて挨拶するの? はい、そう。先 生、おはようございますって。先生、こんにちわって。また、 先生、さようならって。おとなの人にも、こんにちわ、って、 同じようにちゃんと言えるのが正しいのですよ。) 最後の少女は一人だけで歩いてきて、こちらに関心はないと 見受けられたが、そばを通るときに「ヴィーダーゼーエン」とやや尻 上がりに言い、微笑んだ。そしてしんがりに通った先生は、何 も言わなかった。 私は後で(いいお子さんですね、みんな)と言えなかったの を悔いた。 支線に乗り換えた。車両は古い。 先ほどFuldaの駅のReiseZentrumにいた高年のおばさんがも う少し高年のおじさんと一緒に、通路を挟んで私たちの反対側 に席を取った。 この国では車掌がすぐくる。検札時に、問われなくても私は 降りる駅名を告げることにしている。四つ目の駅だと車掌は教 えた。 七つか八つの駅があるはずだし、普通列車は各駅に停車する とばかり思っていたので、駅名に注意を向けていなければいけ ないと思った。 隣りのおじさんは、停まった駅名や自分の降りる駅など私た ちに聞こえるように言ってみたりして、関心や友好の情を示す。 私たちより一停車駅はやく二人は降りていった。 Alsfeldは、木組みの家々を保存している。日本でなら妻籠 とか白川郷というところだろう。信号を右折して町に入るや、 もうそこは木組みの家々がそれぞれ商店を営んでいた。ここの 家並みはロマンチック街道のそれらのように整然とはしていな い。押しあい、もたれあい、木が壁に支えられるほど歪んだり、 目にも分かる傾きがあったりするが、それがかえってネイティ ヴなドイツがここにあると思えるのだった。 レストランの前で町並みを背景に写真やビデオを撮るとき、 ソフトクリームを嘗めながら金髪の少女が珍しそうに見ていた。 手を振って愛想をすると、恥ずかしげに中に引っ込んだ。 町の中心のマルクト広場へと進むと、ワインハウスとその手 前の「赤頭巾の泉」があった。泉の中に童話の「赤頭巾」の像 があるのだが、どう見ても「頭巾」を被っていないのだ。不満 を残しながら広場に出た。 広場を囲む建物は、ワインハウス、足付きの市庁舎、 結婚式の家などで、見回すと面白い印象を残す。いちばん大き な建物には「Deutche Bank(ドイツ銀行)」と白い文字が掲げら れているが、これも木組みの建物だった。 ゆっくり風景を楽しもうかと建物に近づいていって見つけた 物があった。建物の壁に鉄の輪が埋め込まれ、その周囲が異常 にすり減って事の重大さと大きな時の経過とを思わせていた。 そばに寄る人があって、 「(牛か馬か繋いだの?)」と尋ねると、 「(いや、人です。)」 「(罪人?)」 「(そうです。ここに繋ぎ置かれたのです。)」 繋いで裁いたのではない。既決を繋いだのだ。たぶん見せし めだったのだろう。 市庁舎は脚を付けた教会のような姿だ。脚の内側は土間だが、 ここにも繋ぐための金具があった。そしてここのは裁きを受け る者を繋ぐためだと言う。首にも手にも、そして足首にも枷 (カセ)をはめられ鉄の重石(おもし)を引きずって、ここで裁 きを受けたのだろう。 郷土博物館に入る。 この地の女性は、頭上に髪を結いあげて丸めたのを、コップ かお椀かといった感じの髪飾りで覆った。ウイリアム・テルで はないが、頭上に林檎を載せているように見えたり、日本の衣 冠束帯の冠の直立部分だけを頭の頂上に置き、それに懸緒(カケ オ=あごひも)を着けた姿にも似ている。 もちろん近代化する以前の女性の姿だが、小さいものは髪に 丸く密着するし、大きいものでも頭上の載せ物の域を出ない。 これを日本語の「ずきん」に訳してしまったのは誰だろうか。 少女はいつも赤い頭上の載せ物をしていた。だからその愛称 を「赤い頭巾」と訳したとしてもたいして構わないのだが、童 話には挿し絵がある。名古屋の本屋で見たら、防寒用の頭巾で 頭も頬も、そして首や肩回りも覆う「赤い防寒頭巾」をすっぽ りと被った少女が描かれていた。 絵本は、私がはじめて知ったこの地の女性の姿とは全然違っ ている。せめて「赤冠」か「赤キャップ」ぐらいならイメージ が通うのかも知れない。 この「載せ物」をドイツ語では
と言う。 「Rotkäppchen」が「赤頭巾」の本名だから、読者は「赤い頭 上小冠」をイメージしてあげないと「田園交響楽」のすれ違い を、知らず知らずに体験することになる。 正直を言えば私の「赤頭巾」ちゃんは、この時までどちらか と言えば控えめ、はにかみやでおっとり型の少女だった。もし も「頭巾」を脱いだ顔を見たとしたら、色白で柔肌の、赤子の 肌のままの少女だったろう。だが、「頭巾」の事実を知って、 少女は活発で健康に日焼けした、野外を物ともしない少女に変 身した、いやそういう原型を回復しはじめていた。 普顕様を載せる象や金屏風の唐獅子は、今日実物を知る目で 見るとどこかが奇妙だったりおかしかったりする。特に唐獅子 なんかライオンの猛々しさを鈍化させている。 私の「赤頭巾」はもちろん、日本で描かれている挿し絵の 「赤頭巾」のすべてもが、単に普顕様の象、唐獅子と同様の変 形を受けたに留まらず、人物像までが「変性」しているように 思えた。 ところで、幸いにも私には真実への回復が果たされたが、私 の娘や孫も含めて日本の多くの童話好きに、似而非物を与えて 放置されているのが気になった。 昼食は、旅籠屋(はたごや)ふうの木組みの家に入ったが、 中年のウエイトレスにオーダーがなかなか通じなかった。通じ にくければよく聞く努力をすればいいのだが、言葉の端くれで 向こうが勝手に「理解」するから、結論が出かかったころに、 それではない、となる。諦めて適当に妥協したら、「サラダ」 「バター塗りパン」「チーズ・ハムを挟んだパン」「ビール」 になった。 二人で13.8MK(1035\)の昼食だから不満はないが、結局ここで 郷土料理に接することはできなかった。 ☆ |
次章「化学的清潔感」へはここをクリック |