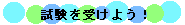 |
トップ画面へ |
| 35.教員試験 |
| 狭き門といわれる教員試験、早めの準備が決め手です。 |
 小学校、中学校、高等学校の違い 小学校、中学校、高等学校の違い | ||||||||||||
| みなさん既にご存じのように、小学校と中学校、高等学校の教諭免許はまったく違います。小学校では一人の教員がほぼすべての 教科を担当するのに対して、中学校・高等学校では各教科を担当します。そのため、免許の種類が異なります。 まずは自分が取得できる免許の種類を確認しましょう。 | ||||||||||||
| (1)小学校教員 小学校教員は、全教科担任制が基本。各教科をはじめ、総合学習や道徳、特別活動のすべてを担任教員が一人で指導するのが 原則です。ほとんどの時間を一人で指導するため、生徒達との結びつきはとても深くなります。 (2)中学校教員 中学校教員は、専門とする教科を学習指導する教科担任制。生徒の生活指導や進路相談、さまざまな学校行事の運営など、仕事の 幅が広いのが特徴です。中学生という多感な年頃の生徒達と向き合う難しさの反面、やりがいもあります。 (3)高等学校教員 中学校と同じように教科担任制ですが、教科は細分化されています。教科指導もより高度で、専門的な知識と指導力が要求 されます。進学や、将来の仕事に関する事など、相談される内容も高度なものになる分、そのやりがいも大きくなります。 (4)その他の免許 *養護教諭普通免許 *幼稚園教諭普通免許 *特別支援学校免許 等 ※特別支援学校の教員は小学校・中学校・高等学校または幼稚園の教員の免許状の他に、特別支援学校の教員の免許状を取得することが 原則となっています。従来、盲学校・聾学校・養護学校ごとに分かれていた教員の免許状は学校教育法などの一部改正(平成19年4月施工) により、特別支援学校の教員の免許状に一本化されました。
|


