![]()
H20.4.23 第307号発行分
・環境保全へ市民ら地道な活動
・県知事賞に大原貴美さん
・〝一点仕上げ〟の絵本原画展
・津市の中北和子さんが初個展
・こちらは「墨の三人展」
・津JCが55周年来月18日に記念式典
・京都へ高速バス運行開始
・「世界の猿文化紀行」を出版
・養生書道サークルが作品展
・今年も一般参加者が体験
・「知ってください動物たちの苦しみ」
・最優秀賞に廣田千浩さん
・津市久居洋画作家協会第2回作品展
・「車いす」寄贈 トヨタL&F中部
・「自分のプロセスを大切に―」
・日舞「亜季の会」発表会
・県民功労者表彰に10人
 |
環境保全へ市民ら地道な活動 5団体に「みえ環境活動賞」 企業が協力し森林保全事業も |
| 主要八カ国の首脳が集まり、地球温暖化などを話し合う「北海道・洞爺湖サミット」まであと七十日余り。今年は京都議定書の二酸化炭素などの温室効果ガス削減義務もスタート。県内各地でも三重の環境を守るための地道な活動が続いている。このほど、市民レベルで取り組んできた五団体が表彰された。未来を担う子どもたちにも、その意識が広がっており、企業と県市町が協力した森林保全事業も七件目の取り組みが始まる。(福家 明子) 里山保全やごみ拾いなど、環境を良くするために活動する個人や団体を表彰する「みえ環境活動賞」。昨年度の表彰式がこのほど行われた。 受賞したのは▽上野生涯学習推進会議(伊賀市)▽内部川清掃実行委員会(四日市市)▽消費者グループたんぽぽの会(多気郡大台町)▽NPO法人・多度自然育成の会(桑名市)▽常磐中学校吉田山ビオトープ(四日市市)の五団体。これまでに八団体が受賞している。 内部川清掃実行委員会は、地域の子どもたちが町内に流れる内部川を清掃して二十三年。今では地域の大きなイベントとして定着、毎年千五百人以上が参加している。 きれいな川を取り戻し、環境意識の向上につながり、特定外来植物の駆除や水生生物の調査もしている。 消費者グループたんぽぽの会は、昭和六十三年九月に住民らで結成。「捨てればごみ、生かせば資源」を合言葉に、廃油による石けん作りなどを続けてきた。 ごみの減量化を目指して、空き缶と牛乳パックの回収も継続。町内に設置した回収場所では、会員約六十人が交代で選別している。 これで得た収益は、町社協を通じて福祉や災害見舞金に。子どもたちへの環境教育にも積極的。 代表の巽幸子さん(71)は「小さなことですが、二十年間続けてきた会員の力は大きい。住民の意識も高まっています」と話す。 ◇ ◇ 県が進める企業による森林づくり「企業の森」に、津市垂水のネッツトヨタ三重が取り組むことになり、このほど県庁で宣言書の調印式があった。 林業の停滞などで荒廃の危機にひんする森林。その再生を目指すもので、企業や社員が資金提供と作業奉仕を。すでに県内の私有林など約一三・五㌶で実施。今回で七件目という。 「ネッツ三重の森」と名付けた森林は、松阪市飯高町の〇・九三㌶。同社の社員や家族が、五年かけて広葉樹の植樹をする。維持管理は松阪飯南森林組合に委託する。 同市内では初めてで、調印式に出席した下村猛・松阪市長は「松阪は七〇㌫が森林。これが生きるかは市政発展の要素」と歓迎。 平野忠良社長(64)は「設立四十周年を迎えた記念事業の一環。地球環境を考えて継続し、次の十年に向かって少しでも役に立ちたい」と話し、一回目の植樹は今月の二十八日。社員ら数十人がコナラ、クヌギ、ヤマザクラなど約二百本を植える。 |
 |
県知事賞に大原貴美さん 花のまちづくりコンクール |
| 鈴鹿市算所五、主婦大原貴美さん(61)の庭が、昨年度「花のまちづくりコンクール」で県知事賞を受賞した。 花のある暮らしや花を通じた町づくりなどの取り組みと作品を表彰するもので、二十二点が審査された。 大原さんは友人宅の庭に刺激を受け、七年前から少しずつ草花を増やしてきた。今では鉢の配置を工夫し、庭全体をデザインするまでに。特に色のバランスに気を配るという。 ほとんどの苗を種から育てており、その管理や水やりに苦労。「いまだに失敗ばかりで…。友人に教わったり、図書館で調べたりしています」と笑う。 四年前からバラも栽培。近所の保育所の子どもや住民が見学に訪れている。 「花の生命力、天候など自然の偉大さを感じている」とも話していた。 そのほかの入賞は次の皆さん。 【団体部門】県知事賞=うどの地区花作りグループ(南牟婁郡紀宝町)▽花の国づくり県協議会長賞=東員花卉くらぶ(員弁郡東員町)【個人部門】県議会議長賞=袴田新作、貞子(鈴鹿市)▽花の国づくり県協議会長賞=藤田幸一(同)、杉本文子(同)、佐藤幸子(伊賀市) |
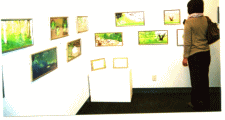 |
〝一点仕上げ〟の絵本原画展 服部さん、上編み平川さんが開く |
| 絵本作家の女性二人が、このほど津市羽所町のギャラリーアスト1で絵本原画展を開いた。 服部美法さん(三九)=鈴鹿市出身=と上平川侑里さん(三九)=桑名市在住=で、「歯の治療を嫌がる子どもに、親しんでもらえる絵本はできないか」という歯科医の話をきっかけに、服部さんが絵を、上平川さんが文を担当して四年前、「もりのちいさなはいしゃさん1」を出版した。 森にある歯医者さんを舞台に、歯医者のネズミと虫歯が痛くて困ったワニが、治療を通じて友情が芽生えるというストーリー。 今回はそのシリーズの二作目。昨年九月に出版した「もりのちいさなはいしゃさん2」の原画二十点と、一作目の原画六点を展示した。 ステンシル技法により一点一点仕上げた水彩画で、森の木々や緑、主人公のネズミやワニをいきいきと表現。繊細に仕上がりと、女性らしいやさしい色使いが訪れた人たちを魅了していた。 また、会期中には作家による絵本の読み聞かせ会もあり、多くの親子連れでにぎわった。 |
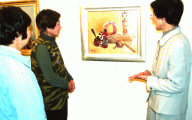 |
津市の中北和子さんが初個展 油絵37点がずらり |
| 津市一身田平野の主婦、中北和子さん(七三)は、このほど同市中央の三重画廊で初の個展を開いた。 描きためた三十七点の油絵を展示。静物画を中心に花や果物、人形のほか、津観音や大王崎の風景画も飾った。 中でもこけしと紙風船などを描いた「お土産」は、風船の素材を表現するのに苦労したという。 八年前から作品に取り組み、同町の画家・駒田幸男さんが主宰する絵画教室で指導を受けており、「駒田先生のおかげで多くの作品ができ、感謝しています」と話していた。 |
 |
こちらは「墨の三人展」 津市の主婦・西田さんら |
| 書を楽しむ主婦三人が、このほど津市中央の三重画廊で「墨の三人展」を開いた。 出展者は杉本幸子さん(60)、西田幸子さん(59)、堀田房子さん(60)。津市八町、書家・川口茜漣(せいれん)さん主宰の「茜会」メンバーで、月に二回ほど創作書道を続けている。 今回は二十八点を展示。一人ひとりが好きな言葉や文字を表現した。 〝樹〟という文字を書いた堀田さんは、緑の葉が茂り、その中に光が差し込む大樹をイメージ。墨の色で力強さを表したという。 |
 |
津JCが55周年 来月18日に記念式典 岩鶴蜜雄氏の講演も |
| 社団法人・津青年会議所(津市丸之内、原田浩伸理事長)は、来月十八日に創立五十五周年の記念式典を行う。 昭和二十八年に設立。明るく豊かな社会づくりを目指して、清掃作業や交通安全の啓発などさまざまな奉仕活動を続けてきた。 青少年育成のための「七夕笹流し」は今年で十九回目。会場となる川の清掃には、市内の企業も参加するほど広がり。 会員で結成した和太鼓チームは、祭りやイベントに出演、地域活性化に一役買っている。 一方、さる十三日には会員とその家族らが、市内の津観音公園にあるステージの壁面に絵を描いた。 同じ場所に十年前に描いたものが劣化し、落書きが増えたためでこれも町づくりの一環。 式典は午後一時三十分から同市大門の津都ホテルで。岩鶴蜜雄・津観音大宝院院家が「地域の絆、人とひととの絆」と題し、ローカルコミュニティーについて講演する。入場無料。 |
 |
京都へ高速バス運行開始 三重交通など 津と四日市から |
| 新名神高速道路を利用し、三重と京都駅八条口を結ぶ高速バスが、先月から運行を始めた。 三重交通(津市)、近鉄バス(大阪府東大阪市)、京阪バス(京都市)三社の共同運行で、一日四往復の津~京都系統、六往復の四日市~京都系統の二路線。津は津駅東口、三重会館、四日市は新正車庫、近鉄四日市駅、生桑車庫から乗車できる。 トイレ付きの大型バスを使い、いずれも所要時間は一時間五十三分。料金は片道大人二千五百円、子ども千二百五十円。往復だと大人四千円、子ども二千円。 初日に行われた出発式は、津と四日市で開催。津では、松田直久津市長らがテープカット。四日市では京都から舞妓さんが来場し、運転士へ花束贈った。 乗車券は一カ月前から予約可能。三重交通の各案内所、営業所、主要旅行代理店などで販売。電話での予約=TEL059(229)5555=も可能。 ○問059(229)5533 |
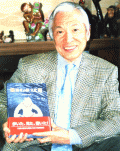 |
「世界の猿文化紀行」を出版 津市の上島亮さんが研究成果まとめる |
| 津市新町、上島小児科院長・上島亮さん(六九)は、三重大学出版会から「驚きの猿文化~世界の猿文化紀行~」を出版した。 自ら世界の猿文化遺産をめぐり、写真を撮り、資料を収集。エジプトとの神猿トト、マイセンの猿楽団、県内の小さな猿の石像など、世界の猿文化から日本の猿文化を紹介している。 幼いころ、村の祭りで奉納する「くくり猿」という赤いぬいぐるみを見て興味を持ち、〝猿の文化史〟について調べるように。仕事の合い間に猿についての文化を求めて、国内や海外の旅を続けてきたという。 上島さんは「世界各地の〝猿の文化〟について興味をもってもらえればー」と話している。 B5判。二百七十ページ。二千五百二十円。県内の書店などで販売している。 |
 |
養生書道サークルが作品展 37回目の今回は50点余を |
| 津市養正小学校PTA会員と、OBらによる「養正書道サークル」は、このほど津市丸之内のNHK津ぎゃらり~で作品展を開いた。 毎年恒例の催しで、三十七回目。漢字や仮名の基本を中心に、創作・実用書道など、学習作品やはがき書道などの小作品約五十点を展示。 中には漂白剤で和紙の色を抜き、文字を表現したユニークなものもあり、訪れた人に書の〝美しさ〟や〝魅力〟を伝えた。 同サークル=中原早苗部長=は、同小学校のコミュニティールームで週に一度活動。西井淡峰氏が指導し、メンバーは十人。村田まち子さんは「これからも楽しんで作品を作っていきたい」と話していた。 |
 |
今年も一般参加者が体験 県手もみ茶技術伝承保存会 恒例の新茶初もみ会 |
| 新茶シーズンを前に、県手もみ茶技術伝承保存会(中森慰会長)は、このほど度会町大野木の宮リバー度会パークで「新茶初もみ会」を催した。 同会は、古来の製茶法である〝手もみ〟技術を伝承保存するため平成九年に発足。伊勢茶シーズン幕開けを告げる毎年の行事。五年前からは、伊勢茶に関心をもってもらうため一般参加者も交えている。 今回は約二十人が参加。西村寿郎さんの茶園で摘み取った約十五㌔の茶葉を蒸した後、四台の焙炉(ほいろ)で手もみ。保存会会員の指導を受けながら「葉振い」「重回転」などの工程を体験した。 参加した玉木さおりさん(三五)は「二年前に茶摘みを体験したことが、手もみは初めて。とっても楽しかった」と話す。 なお、出来上がった約三㌔の茶葉は、参加者が持ち帰ったほか伊勢神宮へも奉納した。 |
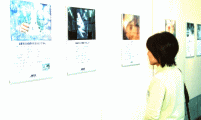 |
「知ってください動物たちの苦しみ」 鈴鹿 JAVAがパネル展 |
| NPO法人動物実験の廃止を求める会(JAVA)=長谷川裕一理事長=は、このほど鈴鹿市神戸の鈴鹿市役所市民ギャラリーでパネル展「知ってください動物たちの苦しみ」を開いた。 同会は昭和六十一年に発足。動物実験の廃止を求める活動を柱に、動物の権利擁護を訴え、海外の動物保護団体とも協力して〝動物の命を守る活動〟を全国規模でおこなっている市民団体。パネル展やマスコミなどを通じて啓発運動などに取り組んでいる。 同展では殺処分や動物実験など動物の「いのち」をテーマに、パネル二十点を展示。国内外のさまざまな動物問題を提起した。 会員の武藤安子(鈴鹿市平田本町)さんは「これからも市民のイベントに参加し、関心をもってもらえる活動をしていきたい」と話していた。 |
 |
サクソホン練習中の生徒ら CD発売の記念コンサート 27日に松阪で |
| 松阪市上川町、ケニーミュージックスクールの生徒らによるコンサートが、二十七日午後七時から同所のレストラン・ケニーで開かれる。 出演は、同校院長でサクソホン奏者、塚本紘一郎さん(69)と塚本さんが率いる「サクソフォーンジャズオーケストラ」。 松阪校、京都校のサクソホン科に通う高校生から六十代までの生徒十数人で構成。昨秋は、生徒が演奏したCDアルバム「スターライト・ドリーム」を製作した。 「普段のレッスンの成果を収録。みんなの夢が詰まったCDができた」と塚本さん。その発売記念で、当日券三千円で、CDも販売される。 |
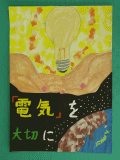 |
最優秀賞に廣田千浩さん 中部電力三重支店 電気ポスター入選作品 |
| 中部電力三重支店は、「電気ポスター」の入選作品をこのほど三重郡川越町の川越電力館・テラ46で展示した。 昭和五十二年に始まった「省エネルギー月間」に合わせて、県内の小学五年生から作品を募集。今回は百六十五校から「電気を上手に使いましょう」「これからの電気」などをテーマに二千七百三十九点が集まった。 入賞者は次のみなさん(関係分、カッコ内は校名)。 ▼優秀賞=廣田千浩(松阪・天白) ▼優秀賞=中西沙耶加(津・立成)、引地巧(松阪・松江)、嶋洸人(同・徳和)、青木優介(四日市・内部) ▼努力賞=足立明日美(津・大三)、和仁拓未(同・高宮)、中村蘭(同・雲林院)、濱口蒼(松阪・徳和)、向井穂高(同)、冨澤怜華(同)、間柄結衣(同・松尾)、田村太誠(同・川俣)、堀口真鈴(同・松江)、刀根拓也(同)、牧野滉平(同)、藤田麻由(四日市・泊山)、杉田拓己(同・神前) |
 |
津市久居洋画作家協会第2回作品展 近年の大作が一堂に |
| 津市久居洋画作家協会(大谷地隆夫会長)の作品展が、このほど津市のポルタひさいで開かれた。 地域の芸術文化の振興を目的に、旧久居市で活動する画家ら十六人の二回目の作品展。近年に描いた30号から100号の大作二十七点が並んだ。 市内や海外の風景を描いたものや和紙を使ったちぎり絵なども。 メンバーの一人、同市一志町高野の長谷川實さん(70)は、ライフワークとして大樹を描き続けている。今回は「命」「飛沫(しぶき)」を出品。 鮮やかで大胆な色使いが特徴で「水を大地から吸い上げて、何百年も生きる木の生命力を表現した。この木のように、健康で楽しく活動していきたい」と話していた。 |
 |
「車いす」寄贈 トヨタL&F中部 社会福祉施設に |
| フォークリフトや総合物流システムの販売・サービスをするトヨタL&F中部株式会社(名古屋市=古田公徳代表取締社長)は、このほど県内の社会福祉施設七カ所に車いすを贈った。 同社では、地域社会から信頼される企業を目ざし、二年前からチャリティーバザーや美化活動、子ども一一〇番の家活動などを展開。 今回は、販売エリアの愛知、岐阜、三重三県下の社会福祉施設・老人介護施設を対象に、初めて車いすを。アルミ製で軽いのが特徴で、今後も続けていきたいという。 贈呈式では中筬重彦・同社取締役が施設の代表者らに目録を手渡した。 |
 |
「自分のプロセスを大切に―」 南山短大名誉教授 星野欣生氏が語る |
| 「パソコンや携帯電話」との関わり方について考える講演会が、このほど津市の県男女共同参画センターで開かれた。 日本心理カウンセリング(同市西古河町)などの主催。人間関係づくりや体験学習を研究する星野欣生・南山短大名誉教授が、「ひとりひとりのプロセスを大切に」と題して話した。 付き合いの希薄化や〝命のモノ化〟など影にある問題点を挙げ、相手とやり取りしていると思っていても、実は一人の作業。関係をつくっているつもりが、関係を追い出している―と説明。 利点を上手に利用する一方で、「人とモノと関わっている自分のプロセス(内面)を意識して」と、参加した約百五十人の教育や医療関係者に呼び掛けた。 |
| 日舞「亜季の会」発表会 来月6日 県総合文化センターで |
| 日本舞踊・西川流鯉風派の発表会「第二十八回亜季の会」が、来月六日午後十二時三十分から津市の県総合文化センター中ホールで開かれる。 東海経済新聞社などの後援で二年ぶりの開催。会主の西川亜季さん、後見人の西川寿々敏さんほか五人と、国の重要無形文化財指定の狂言師・井上祐一氏と長男の靖浩氏が特別出演。津高虎太鼓が友情出演する。 演目は常盤津「双面」、長唄「藤娘」など同派の舞踊九番、和泉流狂言二番、太鼓二番を予定している。 |
| 県民功労者表彰に10人 水谷元伊勢市長ら受章 |
| 第四十四回県民功労者の表彰式が十二日、津市の県文化会館で行われた。 受章者は水谷光男・元伊勢市長(84)はじめ文化や社会福祉、商工業など、各分野の発展に貢献した十人。 鈴鹿市在住の文芸評論家、清水信さん(87)は教員の傍ら戦後すぐ、雑誌「北斗」の刊行や評論活動を続け、昭和三十七年に近代文学賞を受賞。自宅に設けた「全国同人雑誌センター」で研究会を開き、地域での文学交流に努めてきた。 昭和四十年からの受章者は四百八十二人六団体になった。 そのほかの受章者は次の皆さん。 森田治(79)=四日市市、元県議会議員▽石井洋子(73)=名張市、元県民生委員児童委員協議会長▽藤田治美(82)=桑名市、元県保護司会連合会長▽山路啓雄(76)=志摩市、元県調理師連合会長▽鯉江盈(76)=津市、県商店街振興組合連合会理事長▽中嶋正(78)=四日市市、県茶業会議所会頭▽堀江順一(80)=名張市、県農業会議会長▽石橋通之進(68)=ブラジル、ブラジル県人文化援護協会長 |
[ バックナンバー ]
